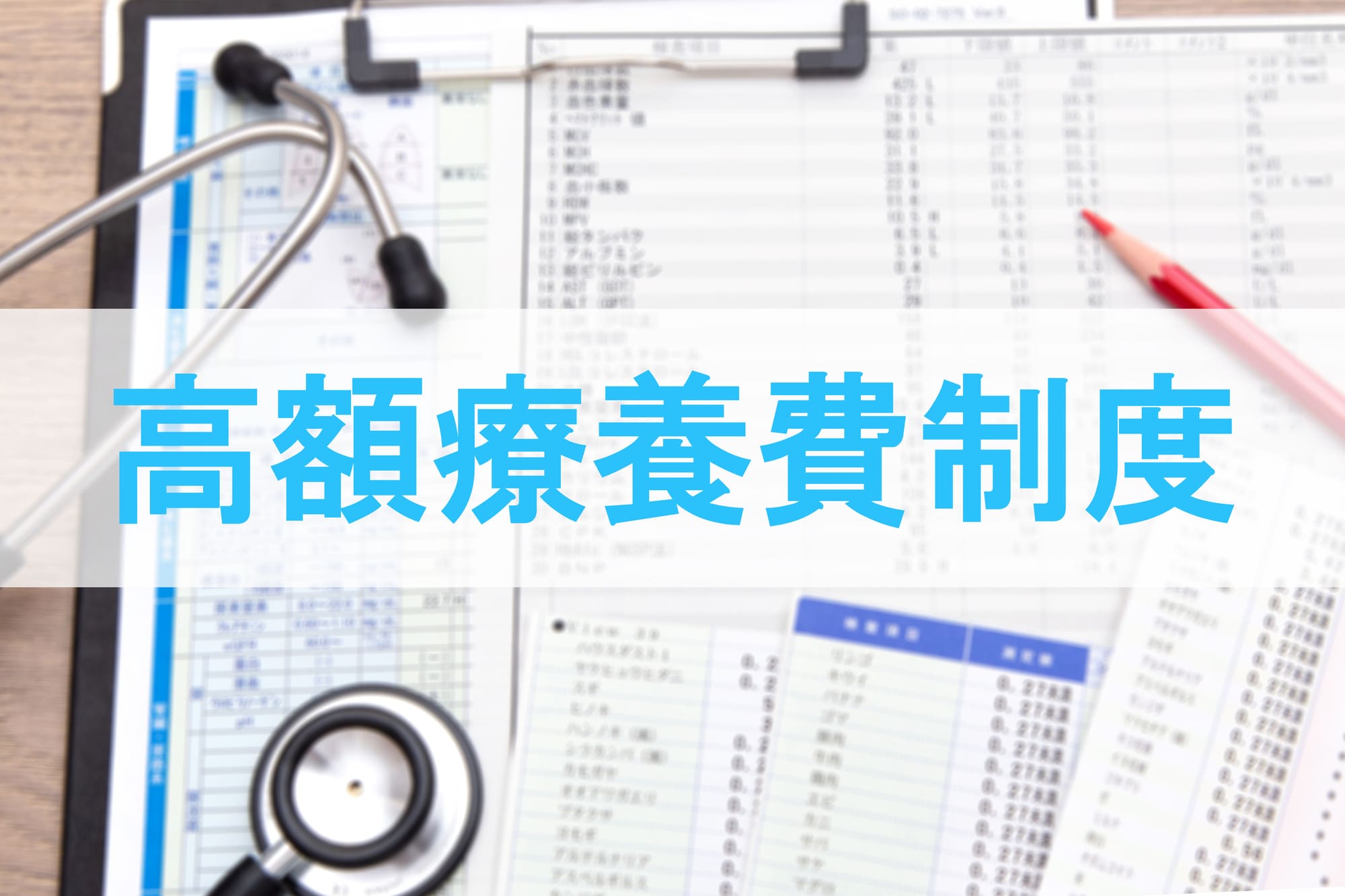「思ったより医療費が高額になってしまった…」
「毎月の診察で出費がかさむ」
そんなときに活用できるのが、高額療養費制度です。
本記事では、高額療養費制度の詳細や申請方法、活用事例をわかりやすくご紹介します。
とどくすりでも高額療養費制度は活用いただけるので、今後のご利用についても併せてご検討ください。
高額療養費制度の基本概要(概要、制度の目的)
高額療養費制度は、医療費による経済的な負担を軽くするための制度です。
1ヵ月間(1日から末日まで)で支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、超過した金額が払い戻されます。
高額療養費制度の適用条件
1ヵ月の医療費が自己負担の限度額を超えていることが最低条件で、保険適用となる医療費のみ(自由診療による医療費や食事代、部屋代などを含まない)が対象です。
そこで気になるのが自己負担の限度額ですが、公的医療保険に加入している人が70歳以上かどうかや年収などによって金額が異なります。
69歳以下の場合は、所得区分に合わせて世帯ごとにひと月の上限額を計算します。
- 年収約1,160万円以上:25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
- 年収約770万~約1,160万円:16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
- 年収約370万~約770万円:8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
- ~年収約370万円:5万7,600円
- 住民税非課税者:3万5,400円
70歳以上の場合は、所得区分に合わせて世帯ごとに以下の方法で計算しますが、外来だけの上限額もあります。
- 年収約1,160万円以上:25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
- 年収約770万~約1,160万円:16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
- 年収約370万~約770万円:8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
- 年収156~~約370万円:5万7,600円、外来1万8,000円
- 住民税非課税世帯:2万4,600円、個人なら(外来)8,000円
- 住民税非課税世帯(80万円以下):1万5,000円、個人なら(外来)8,000円
複数の医療機関での支払いや、同じ医療機関で複数回の支払いを1ヵ月単位で合算できるほか「世帯合算」もできます。
世帯合算は、同一世帯で同じ公的保険に加入している人の医療費を合算でき、69歳以下だと1回に2万1,000円以上の支払いが対象です。
高額療養費の申請方法と必要書類
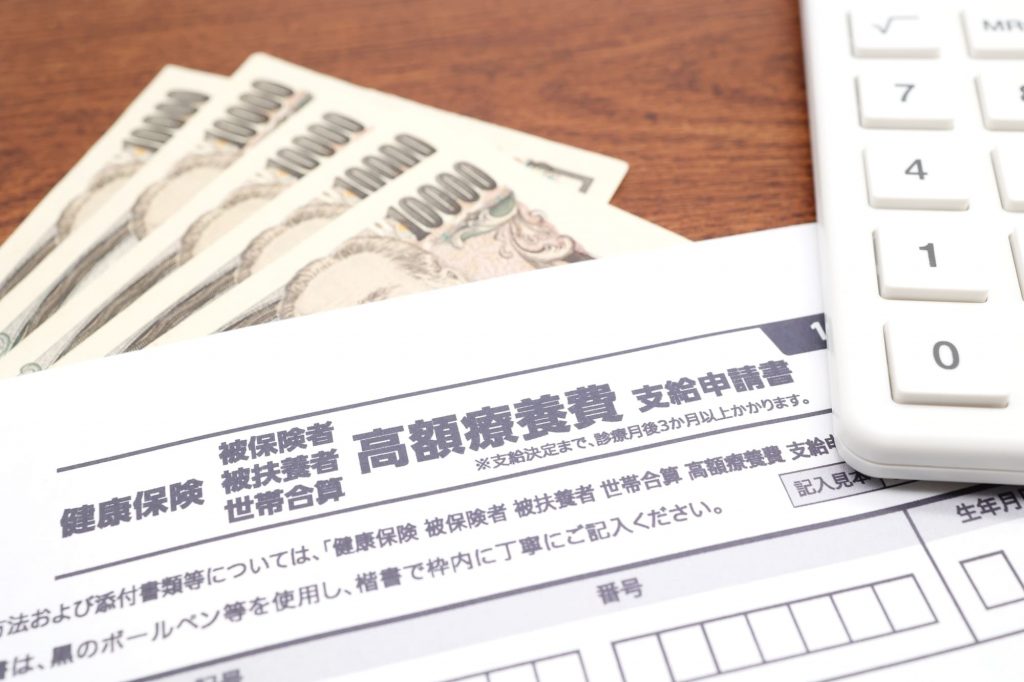
高額療養費の支給を受けるには、健康保険組合や協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、後期高齢者医療制度、共済組合など、加入している公的医療保険へ申請します。
申請方法は「事前申請」と「事後申請」の2通りです。
事前申請は、入院するときに健康保険限度額適用認定証を医療機関に提出する方法で、入院前に申請して取得しておく必要があります。
入院中や退院時の支払いは、高額療養費制度によって差し引かれた金額のみです。
事後申請は、退院時に健康保険による自己負担割合を支払った後に高額療養制度の申請を行います。
自己負担の限度額を超えた金額を、加入している公的医療保険が振り込んでくれます。
高額療養費制度を活用する具体的なケースとメリット
ここでは、医療機関をよく利用する方がどのように制度を活用できるか、具体的な例をもとに紹介します。
慢性疾患での活用例(糖尿病・高血圧・リウマチなど)
糖尿病や高血圧、リウマチなどの慢性疾患では、長期にわたって定期的に診察や検査を受けるため医療費の負担が大きくなります。
過去12ヵ月間で3回以上、世帯合算した医療費が高額療養費制度の対象になった場合、4回目以降は「多回数該当」となり、その月の自己負担金額がさらに下がります。
たとえば、6・10月、翌年1月に医療費が自己負担限度額を超えた場合、5月まで(12ヵ月以内)に医療費が自己負担限度額を超えると、負担する医療費が安くなります。
69歳以下の多回数該当は、所得区分に合わせて世帯ごとの自己負担限度額が下がります。
- 年収約1,160万円以上の場合:14万100円
- 年収約770万~約1,160万円の場合:9万3,000円
- 年収約370万~約770万円の場合:4万4,400円
- ~年収約370万円の場合:4万4,400円
- 住民税非課税者の場合:2万4,600円
70歳以上も上記と同じ所得区分で同じ自己負担限度額ですが、住民税非課税者には多回数該当は適用されません。
手術・入院時の医療費軽減シミュレーション
入院して手術を受けた月の医療費を100万(保険外診療や食事代、部屋代などを除く)払ったとすると、健康保険が3割負担であれば30万円支払います。
69歳以下で月収が28~50万円の場合、年収約370万~約770万円の計算方法「8万100円+(100万-26万7,000円)×1%」なので、自己負担限度額は8万7,430円になります。
高額医療費制度で戻ってくる金額は、実際に支払った30万円から8万7,430円を差し引いた212,570円です。
医療費控除との違い

医療費控除は、1月1日からの1年間で支払った医療費が一定額を超えたときに、所得税や住民税などが軽減されるものです。
医療費控除の場合は保険適用外の医療費も含まれ、10万円を超えた場合のほとんどが対象となります。
高額療養費とも併用でき、支給金額を除いた医療費を税務署へ申告します。
高額療養費制度の活用は「とどくすり」で
処方せん薬宅配サービス「とどくすり」を利用すれば、薬局へ足を運ばなくても自宅などご指定の場所で処方薬を受け取れます。
薬を受け取るための待ち時間がなく、体調が悪いときや忙しい合間に受診するときにも助かるはずです。
また、受診による精神的な負担を軽くしたいというときにも「とどくすり」が役立つでしょう。
高額療養費を申請するためには、ひと月に支払った医療費を世帯全員分把握しておかなければなりません。
とくに慢性疾患をお持ちの方は定期的に医療費の支払いが発生するため、医療費の管理を毎月するのは大変です。
「とどくすり」では、ご本人以外にもお子様さまや年配の親御さまなど、ご家族の登録も可能です。
ご家族分の医療費の支払いをカードや銀行振り込みなどで一元化でき、世帯全員の医療費をすぐにチェックできます。
カード決済なら「あと払いbyとどくすり」で、病院やクリニックの受診料と薬代を合わせて支払え、病院で会計待ちする時間もなくなりとても便利です。
また、オンライン服薬指導なら家族にも同席してもらいやすく、病状や薬の必要性などを共有しやすいでしょう。
関連ページ
「とどくすり」のサービス概要ページ
「とどくすり」の利用方法ページ
高額療養費制度×とどくすりで賢く医療費を抑えよう
「とどくすり」を利用すると、一人ずつ領収書を集めて医療費を合算するなど高額療養費制度の申請に必要な手順が少なくなります。
また、家族の医療費をまとめて支払える機能も活用すれば、離れて暮らすお子様やご両親の医療費も把握しやすいでしょう。
診察後の会計待ちや薬局への移動、薬の受け取りなどの時間短縮ができるため、空いた時間を有効活用できます。
とどくすりは、薬局へ行かずに処方せんの薬を宅配便で受け取れるサービスです。
処方された薬についてはオンラインで薬剤師から説明を受けられるため、ネット環境がある場所であれば、どこからでも処方薬について問い合わせることができます。
是非とどくすりの活用をご検討ください。
参考文献
-
- 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保」
-
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」